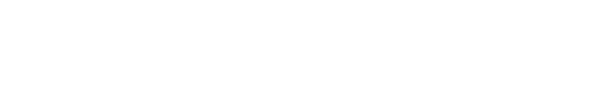インテリアアーキテクチュア&デザイン科1年
津谷鈴音
1999年生まれ 東京都出身
2017年 私立あずさ第一高等学校卒業

物事を掘り下げて見える新しい世界
将来像がうまく描けなかった高校時代。「専門学校でやりたいことを見つけよう」と視野を広げて進路を検討するなか、ICSのオープンキャンパスに。ノートづくりを体験したのですが、それが楽しく、入学の決め手となりました。
授業ではインテリア・建築・家具の3分野で、理論に実技、デザインと幅広く学びます。特に印象的だったのは「支えるかたち」という課題です。木製合板で椅子を作ったのですが、デザインにはじまり製作手法の考案、木の切り出しから組み立てまでを、すべて自分で行うので本当に大変でした。それだけに完成した時は、これまでに感じたことのない達成感がありました。
アイディアと技術両方が必要とされる課題が多く、考えを形にする難しさを実感しつつ、同時に物事を掘り下げて考える面白さにどんどん魅了されています。まだまだ未熟ですが、「作りたいものを思いどおりの形にできる自分」をめざして、ますます頑張っていきたいです。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科1年
中畑美咲
2000年生まれ 東京都出身
2018年 東京都立工芸高等学校卒業

五感で学ぶ
高校時代、映画の大道具デザインに興味を覚えて、インテリアと建築を両方学べる本学科に入学しました。
ICSでは理論や技術とともに「見る」「触れる」といった“自分の感覚を通じた学び”を大事にします。人が住む場所、過ごす場所をデザインするには作り手の豊かな感性が欠かせないからです。スケッチ、撮影、フィールドワーク、素材収集……教科書から飛びだした刺激的な学びが視野をぐんと広げてくれます。
入学当初は家具にだけ焦点を当てたりと空間を小さく考えがちだったのですが、今は構造や素材も含めて大きく捉えられるようになりました。ICSの先生方は生徒と真剣に向き合ってくださるので先生の言葉から自分の強みや個性に気づく機会も多く、課題を通して作品を作るごとに考えが深まり成長の手応えを感じます。
この1年で自分のデザインの輪郭、めざす方向がぼんやりと見えてきましたが、まだまだこれから。これからも時間を大切に頑張りたいです。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科2年
池田絵里
1998年生まれ 神奈川県出身
2016年 神奈川県立麻生高等学校卒業

幅広い種類の課題で自分の得意を見つける
インテリア・建築・家具と幅広く学べ、デザインや発想力の育成に注力している。「この学校なら自分の将来がきっと広がる」と、ICSを選びました。
入学後は大げさではなく自分がガラリと変わりました。空間づくりは建物はもちろん、色や物、素材、そして人間や取りまく環境すべてが対象ですから、興味が尽きることはありません。また2年生からは授業もぐっと専門性が深まります。学校近くの土地を課題に家族構成などを綿密に考えた住空間の設計や店舗設計に取り組む企業との産学提携プロジェクト。そんなリアルな社会と結びついた課題をこなすことで、自分の得意・不得意も見えてくるので、将来の道を考える上で大きな参考になります。
次は3年生。集大成である卒業研究制作が始まります。テーマはまだ未定ですが、例えば住空間であり商空間でもある「ホテル計画」は面白そうだと思っています。苦労すると思いますが、最後まで諦めずに必ず成功させたいです。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科2年
伊原 直
1994年生まれ 東京都出身
2014年 私立和光高等学校卒業

何故?が空間デザインの質を高める
ビジネスを学びに留学していたアメリカで、前衛建築「ウォルト・ディズニー・コンサートホール」の素晴らしさに心を揺さぶられました。作った物が未来に残る建築分野に惹きつけられ進路変更をして帰国。相談したデザイン業界の知人から「建築・インテリア両方が学べて必ず力になる」と強く勧められICSに入学しました。
初めてづくしの1年生を経て2年生からは学びのステージが数段アップします。インテリア・家具だけでなく建築・ランドスケープまでという風にスケールが大きくなり、構造はもちろん壁の厚み、窓のおさまり、建設のしやすさ……細部まで実際に建設できるレベルの設計が求められます。「カッコいい」と表層的ではなく「なぜこの素材を使う?」など自問しながら空間の隅々まで意図のある設計をするようになり、デザインの質が上がったのを実感します。
将来の目標は建築家。学生時代に知識・技術・センスを磨けるだけ磨いて、着実に近づいていきたいと思います。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科3年
青木茂久
1989年生まれ 茨城県出身
2009年 茨城県立岩井高等学校卒業
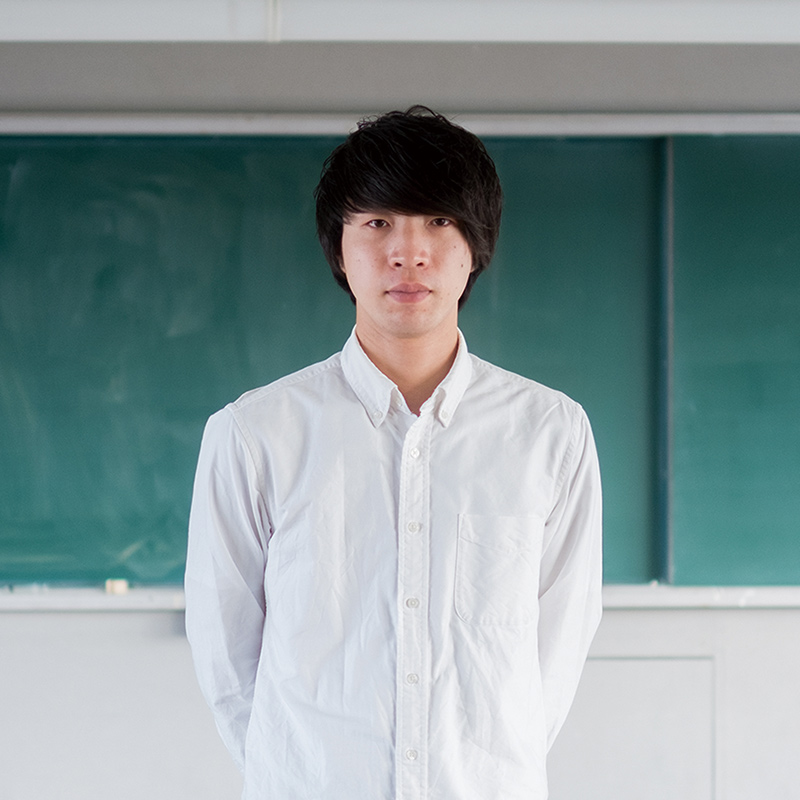
手と頭で考えることでデザイン力を伸ばす
インテリア・建築を深く勉強したいと考えていた僕にとって、プラスして家具まで学べるICSは最適の学校でした。「この3年間で学べるだけ学んでやる」。高校卒業後、6年の社会人生活を経ての入学でしたので、そんな意気込みで入学しました。
デザインは「頭で考える」「手で考える」の両方が必要です。デザイン理論を学び、発想から製作までを自分で行うICSのカリキュラムでは、手と頭を双方向的に使うことで「デザイン力」を飛躍的に成長させてくれたと思います。1年生の時には「いったいなぜこんなことするのだろう?」と感じていた造形やデザイン理論の授業が、実は自分の作品づくりの芯になっていたりと、全てが身になる授業の濃さを進級するにつれて実感しました。
将来は独立して「今までにない新しい形の設計事務所」を開きたいです。在学中に描き始めたこの夢を、自分なりに少しずつ叶えていこうと決意を新たにしています。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科3年
逸見優斗
1998年生まれ 山形県出身
2016年 山形県立寒河江工業高等学校卒業

地道に作業を積み重ねることの大切さを学ぶ
ある著名なカーデザイナーの講演で、デザイナーという職業を知った高校時代。建築系が良いと複数の学校を回った結果、素人目にも一目瞭然なほど作品のデザイン力が群を抜いていたのがICSでした。第一線で活躍している先生の直接指導も魅力でしたね。
一見華やかなデザインの世界ですが形にするのは実に大変で、入学当初は「やっていけるのかな」と心配でしたが、逃げずにコツコツ取り組み続けた結果、徐々に手応えを感じ始め「この世界で生きていく」と決意するまでに。
卒業制作では「食物アレルギーをもつ人のためのレストラン」をテーマに、リサーチから製図、模型づくり・プレゼンテーションまで学んだ全てを注ぎ込め、3年間の集大成となる作品ができました。
いま2級建築士の勉強中で目標は住宅・家具・プロダクトの設計ができる人間になること。いよいよ社会に足を踏み出すので、コツコツがんばり続けて目標を必ず叶えます。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアデコレーション科1年
菅原 空
1999年生まれ 神奈川県出身
2017年 神奈川県立横浜旭陵高等学校卒業

親子2代でICS
実は母もICSで学んだ卒業生。他のインテリア系の学校も見た上で、デザインに注力している点に惹かれ、親子二代にわたってのICSの学生となりました。
主に空間デザインを学んでいますが、何もないところに発想が生まれてアイディアが広がる瞬間がワクワクします。お店のコンセプトから装飾までを考えるなど、デザインの本質から考える授業が多いので頭はフル稼働です。「スタイル実習」も大好きな授業のひとつ。写真を一枚選び、その空間に写る素材すべてを見極めて実際にサンプルを集めるため、「見る力」「推理・分析する力」が鍛えられ、自分の空間づくりにも役立ちます。「創造力を高められる学校だよ」と母から聞いていましたが、まさにその通りでした。
将来は人が住む環境をデザインしたいと考えています。発想、センス、知識……。魅力的な空間づくりには複合的な力が求められるので、もっともっと自分の引き出しを増やさなくてはと思っています。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアデコレーション科1年
丸山綾華
1998年生まれ 埼玉県出身
2016年 埼玉県立所沢高等学校卒業

意識しながら「見る」ことで変わる世界
家と学校を漫然と往復する日々に疑問を感じて大学を退学。何が好きかを考えた時に出たのが「インテリア」という答えでした。
数校を比較して最も深く学べると感じたICSに入学しました。1年生は商空間や住空間等のインテリア制作を学びますが、空間デザインはもちろん図面・模型作製まで手がけ、しかも課題数が多いので正直大変です。先生や同級生との議論、街に飛び出すことも多く、講義を聞くだけの一方通行な学びを大学で経験していたからこそ、この環境がいかに貴重かを痛感します。
漫然と過ごしていた自分から、自主的に勉強をする自分へ。入学後の変化は色々ありますが一番は視点の転換です。当然ですが人工物には必ずデザイナーがいます。素材や形に込められた意図を考えながら歩いたり、街、物、世界の見え方が180°変わりました。以前からはまるで想像もしなかった自分ですが、充実感いっぱいです。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアデコレーション科2年
宮澤芽衣
1998年生まれ 静岡県出身
2016年 静岡県立三島南高等学校卒業

プロの現場を知る厳しい先生、だからこそ響く言葉
建設業を営む父の背中を見て育ち、もともと建築やインテリアが大好きでした。進学先はかなり調べましたが、ICSほど建築やインテリアを集中的に学べる専門学校は他になく、「ここだ」と高校2年生の時には入学を決めていました。
ICSではデザインを考える時間が長く、また素材に触れ、街やショールームに積極的に赴くなど「体感の機会」も多いので、大学の建築学科や他校でデザインを学ぶ友人から羨ましがられます。数週間に一度は課題提出があり常にインテリア漬け。当初は大変でしたが、頑張って乗り越えたことで大きな自信になりました。卒業研究制作ではこれまで一度も褒めてもらえなかった先生から褒めていただけて、とても嬉しく、成長の手応えを感じることができました。
卒業後はリノベーションを担う会社に就職予定です。現場に行く機会も多く、構造躯体の裏側が知れるのでワクワクしています。私を成長させてくれたICSの学びを社会で実践していきたいと思います。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアデコレーション科2年
中島望美
1993年生まれ 神奈川県出身
2015年 成城大学卒業
銀行勤務を経てICS入学

住宅と商業、どちらも経験したから開けたこれからの道
住宅の間取りや家具の配置などを考えるのが好きで大学生の時の就職活動で住宅系の会社を受けていました。結局当時は銀行へ就職し2〜3年ほど働いたのですが、インテリアへの興味を捨てきれず、改めて勉強をしてみようと決意し、いくつかの学校へ見学に行きました。最終的にインテリア専門の学科があることと卒業と同時に2級建築士の受験資格が得られることが決め手となりICSへ入学しました。
入学当初は住宅系へ進むことを志望していましたが、色彩や素材を選び、空間のスタイルを作り上げていく『スタイル実習』や『素材研究』などの授業を通して素材や色彩の面白さを知れたことで、より多くの素材を扱える商業店舗の設計に就きたいと考えるようになりました。
卒業後は美容室の設計を主に行う設計会社へ内定が決まっています。就職してからも素材の知識や使い方をより深く知って、クライアントが思い描いている以上のデザインを提案できるようになりたいです。
卒業後はリノベーションを担う会社に就職予定です。現場に行く機会も多く、構造躯体の裏側が知れるのでワクワクしています。私を成長させてくれたICSの学びを社会で実践していきたいと思います。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアマイスター科1年
塚本紗奈
1999年生まれ 東京都出身
2017年 私立日本工業大学駒場高等学校卒業

原寸大の製作実習だからリアルな学び
幼い頃からモノづくりが大好きでした。インテリア分野の数校からICSのマイスター科を選んだのも「モノをつくる」「手を動かす」を重視した方針に惹かれたからです。
授業は一言でいうと実践的。小屋や椅子を原寸大で製作したり、IFFTというイベントで展示スペースの設置を学生が丸ごと手がけたり、リペアの授業では学校の地下ラウンジを修繕しました。実際に手を動かして形にすることは何よりの勉強ですし、失敗にも「どう改善しよう?」という学びがある。各授業でその道のプロの職人さんから技術指導を受けられる機会も多く、モノづくりをめざす人間にはこの上ない環境だと思います。
将来の目標は内装系の仕事に就くこと。作り手として納得できる仕事をするのはもちろん、お客さんと本音で話して満足してもらえる仕上がりを届ける仕事人が理想の未来の自分です。めざす未来に一歩ずつ近づけるよう毎日の授業を頑張っていきたいと思います。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアマイスター科1年
糸井一茶
2000年生まれ 栃木県出身
2018年 鹿児島県立屋久島おおぞら高等学校卒業

失敗こそが成長のきっかけ
幼い頃から建具職人である父の背中を見て育ち、自分も職人の道を志してICSを選びました。モノづくりの技術と知識両方が習得できるカリキュラム、各分野のプロから直接手ほどきを受けられる授業、リアルスケールで製作できる環境。目で、手で、耳で学べる体制が整ったICSはモノづくりを志す人にとって理想の場所だと思います。入学後どんどんモノづくりに魅せられますし、授業がない日も来たくなる、そんな学校です。
まだまだ未熟なので失敗もたくさん。ですがこの失敗こそが大事だと考えるようになりました。例えば木材が割れたとしたら、なぜ割れたのか?どうリカバリーするか? 反省して、考えて、次に活かす。ただ漫然と手を動かすのではなく、考えながらモノづくりをする。そんな繰り返しが自分の糧になっていく手応えがあります。学生生活は残り1年。恵まれた環境にいる内に吸収できることはすべて吸収する心意気で過ごしていきたいです。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアマイスター科2年
佐野脩斗
1997年生まれ 神奈川県出身
2015年 私立湘南工科大学付属高等学校卒業

ものづくりの奥深さを知った2年間
幼い頃から建築やモノづくりへの憧れがあり、自分も「作る仕事」をしたいとICSへ入学しました。
入学後は、簡単に見えたことが難しかったり、自分で作れると思ったものがまったく作れなかったり。モノづくりの奥深さと難しさを痛感しましたが、日に日に技術も向上し、構造や荷重など一歩踏み込んだ知識を教わった上で製作するので、説得力あるモノづくりができるようになりました。
1年生の時には「よくできた」と感じていた自分の製作物も、2年生になって見ると粗がいっぱいで(笑)、それに気づけた自分に成長を実感しました。ICSが参加するIFFTというイベントでは、2年生が指導役となり1年生とブースを作るので、現場での指導力も鍛えられました。
卒業後は施工管理の企業に就職が決まっています。建物も家具も、何年、何十年とこの世に存在するもの。いつか自分の子供に「これはお父さんが作ったんだよ」と胸を張れる良い仕事をしていきたいです。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアマイスター科2年
飯塚恵理
1993年生まれ 島根県出身
2011年 私立明誠高等学校卒業
工場勤務を経てICS入学
左官会社 内定

幅広い「ものづくり」の経験で広がる選択肢
「多能工の育成」を掲げるマイスター科の魅力は私たち学生の可能性を広げてくれること。家具製作、建築、内装、電気関連……。一言でモノづくりといっても多彩ですが、幅広く学ぶことができ、自分に合うモノづくりを見極めることができます。またインターンの機会も多く、興味を覚えた業界を体験・比較した上で将来を具体的に選べるので、どの道に進むにしても、多くのモノづくり体験は必ず役立ち支えになってくれると思います。
私自身、視野が広がり将来が大きく変わりました。島根での社会人経験を経て入学した時は、「モノづくり=家具製作」の印象で家具職人になるつもりでしたが、授業で初体験した左官作業が面白くてすっかり方向転換。この道だと確信し、卒業後は左官職人として歩み出します。
ICSで学んだからこそ納得して掴みとれた未来。一日も早く一人前になり「現場をまかせてもらえる職人」になることが今の目標です。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科II部1年
中丸愛梨
1992年生まれ 東京都出身
2016年 多摩美術大学卒業

デザインとは何か?
美大の油絵科を卒業後、インテリアデザインを学びたくて入学しました。決め手はインテリアと建築の両方を学べること、そして2級建築士の資格がとれるという2点。尊敬するインテリアコーディネーターの方に「建築の知識がインテリアデザインの質と仕事の可能性を広げる」と以前言われていて、その学びの環境があったのがICSでした。
「デザイン=問題を解決すること」と言われます。入学後の初課題で造形的な照明を作ったところ「形が生々しい」という言葉で、照明としてはどうか?と講評を受けたんです。それまでアートの世界にいた私に、「デザインとは何か?」と問われたようでハッとしました。そこから誰かが抱える問題に自分なりの答え(デザイン)を提案したいと、一段深く考えるようになりました。
学ぶことも多く、アルバイトとの両立は大変ですが、できない理由を探していたら何もできません。すべてを吸収するつもりで、ICSでの時間を大切にしていきたいです。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科II部1年
水谷 創
1991年生まれ 埼玉県出身
2014年 東京理科大学卒業

斬新で面白いモノを。柔軟な発想力を養う
理系専攻だった大学時代に畑違いの建築・インテリア分野に強く惹かれるようになり、卒業後は家具メーカーに営業職として就職。設計施工会社を経て数年の社会人経験を積んだ頃、「デザインを本格的に学びたい」とICSの夜間部へ入学しました。
「オンリーワンをつくれ」。初課題でどこかで見たようなデザインを提出した私を叱った先生の言葉。ショックでしたが、自分でも納得の出来ではなかったので腑に落ち、真剣に学ぶ腹が決まりました。自分だけのモノが作りたい、斬新で面白いモノを。柔軟な発想力を養うために、アートや制作物、日常風景、目に映る全てからヒントを得てやろうと常にアンテナはON。見て、感じて、考える日々を送るうちにデザインの質も顕著に変化しました。奮起のきっかけをくださった先生に今も感謝しています。
貪欲なチャレンジ精神を忘れず、一歩一歩自分を高める努力を続けていきたいと思います。
(インタビュー 2019年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科II部2年
田和直人
1993年生まれ 兵庫県出身
2015年 成蹊大学卒業

飛び込んだからこそ広がった世界
「本当にやりたいこととは?」。大学卒業後、建築コンサルティング企業で地図制作の仕事に関わるうちにわいた疑問に、「家具デザインがしたい」と答えが出た時、会社を辞めてICSへ入学しました。家具だけでなく建築・インテリアを同時に学べる環境が良いと思いました。
高いデザイン性と何か問題を解決する“+α”の価値がある家具。そんな「Recreate」が入学当時からめざす家具づくりです。といっても当初は思い通りの制作ができず、先生方からの叱咤激励と親身な指導が成長を後押ししてくれました。おかげで卒業制作では、近未来の過密化する都市生活を想定した「ストレージデスク&チェア」を制作でき、機能・デザインに満足ゆく仕上がりが得られました。
将来の目標は自分のオリジナル家具の販売です。以前にはとても考えられなかった未来ですがこの2年が新しい扉を開いてくれました。卒業後は海外のインテリア事務所への就職にチャレンジする予定です。
(インタビュー 2018年2月)
インテリアアーキテクチュア&デザイン科II部2年
古瀬日菜子
1996年生まれ 神奈川県出身
2014年 神奈川県立藤沢西高等学校卒業
武蔵大学在学中
家具メーカー 内定
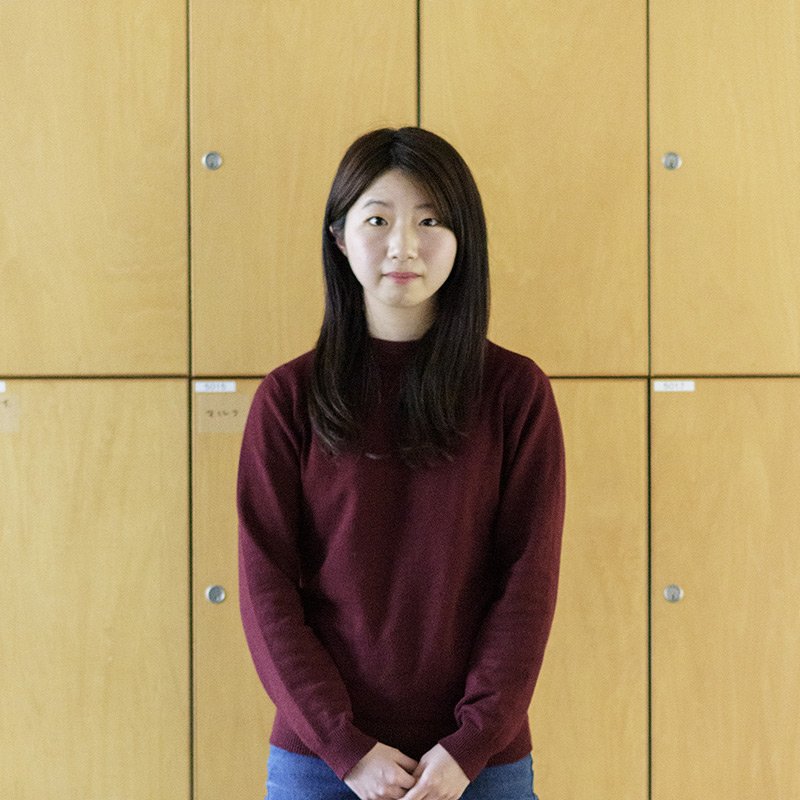
大学に通いながらの2年間。大学とICSの学びを掛け合わせて開けた未来
夜間部は年齢や背景が様々な生徒が通います。大学の経済学部に在籍する私は、好きなインテリアに関係する職業に就きたいと考えてICSに入学。授業は平日夜の3日、さらに欠席した場合は土曜日に補講が受けられるとあって、大学と並行して学びやすい環境だと考えました。
授業の魅力をひと言でいうなら「相互成長」です。建築とインテリアの2分野で、さらに知識(頭)と技術(手)の両方を学べるため掛け算のように理解が増幅します。頭だけで考えて行き詰まっていた課題が、手を動かすことで解決していった経験が何度もあります。その逆も同じでバランス良く頭と手を鍛えることが大事だと実感しました。
ICSの2年間の学びのおかげで自信をもって就職活動に臨むことができ、卒業後は家具メーカーに入社します。家具制作・販売・店頭デザイン・イベント企画など幅広く挑戦できる環境ですので、多くの経験を積み、制作から経営までを理解できる人間になることが目標です。
(インタビュー 2019年2月)